あくび「欠」の部首は?意外と知らない漢字の構造を分かりやすく紹介
あくびという、誰もが日常的に経験するしぐさ。
その何気ない行動を漢字で表記すると、「欠」と書くことができるのですが、一瞬迷ってしまうことがあるかもしれません。
さらに、この漢字「欠」の部首が何なのか、パッと答えられる人は案外少ないのではないでしょうか。
漢字は部首によって大まかな意味や分類が分かれ、それぞれに奥深い由来があります。
この記事では、「あくび」の漢字「欠」について、その部首に注目していきます。
普段はあまり意識しない言葉の裏側に、どんな漢字的な背景があるのかを知ることで、日本語の面白さや奥行きを再発見できることでしょう。
知らずに使っていた言葉に、新しい光を当ててみませんか?
「あくび」を表す漢字とは?
「あくび」という言葉を漢字で表すと5つの表記があるんです。
「欠伸」「呿呻」「呿」「欠」「𡙇」の5つです。
ただ、辞書などを紐解くと、主に「欠」や「欠伸」が使われることがわかります。
まず、「欠」という漢字の形を思い浮かべてください。
まるで、口を大きく開けている人の姿のようにも見えませんか?
「欠」はもともと口を開けて何かを発している人の姿を象った象形文字で、「あくび」そのものを視覚的に表したものとされています。
「あくび」をしているときの顔つきにどこか似ているのも、なるほど納得です。
さらに、丁寧に表現する際には、「欠伸」という二文字が使われることもあります。
「伸」は「体をのばす」動作を示しており、あくびをしながら体を伸ばす様子をよく表現しています。
普段はひらがなで書かれることが多い「あくび」ですが、その裏には漢字ならではの動作や姿をとらえた深い意味が隠されているのです。
今回は、「あくび」の一文字の漢字「欠」にスポットライトを当てて、部首等を探っていきます。
※「あくび」の漢字については、既に記事をアップしています。
⇒ あくびの漢字は?「欠伸」以外の表記が見かけない奴ばかりで面白い
あくび「欠」の部首は?
「欠」という字のどの部分が部首なのか、じっくり見ていきましょう。
ここで注目したいのが、この「欠」という字がそのまま部首としても使われるという点です。
漢字の世界では、こうした「意味を持つパーツ」が部首と呼ばれ、辞書で漢字を引くときの手がかりにもなります。
部首「欠(けつ・けん・あくび)」は、「欠」を含む漢字や、あくびをする・からだをかがめる動作に関する漢字が集められています。
旁になるときは、特に「けんづくり」と呼ばれます。
つまり、「あくび」を表す「欠」という漢字の部首は、まさにその字全体「欠」そのものなのです。
この部首を持つ漢字は、口や体の動作、感情の表現など、人間的な要素が多く込められているのが特徴です。
例えば、「歌」や「次」、「欲」などの漢字にもこの「欠」の部首が含まれています。
これらはいずれも「動作を伴う」といった意味が共通しており、「欠」という部首が意味的なヒントになっているのが分かります。
「欠」もうひとつの意味
ただ、「欠」には、起源の異なる別々の漢字が、たまたま同じ形になった例でもあります。
「欠ける」と訓読みする「欠」は、本来、「缺」が正式な文字でした。
部首は「容器」を表す「缶」で、元々の意は「容器の一部が壊れる」だったのです。
そして、本来、「欠」の意が「あくびをする」ことから変化して「満足していない」から「不足する」までを包含することになり、「缺」の意と似ていることから、「缺」は「缺」の略字としても使われることになったのです。
※他にも、次のような部首で記事を書いています。
⇒ 部首「おおがい」とは?意味から成り立ち・使われる漢字まで総特集
⇒ 部首「れんが」とは何か?その意味からどんな形・由来までを総特集
⇒ 部首「ネ」とは何?読み方から意味・使われる漢字の特徴をご紹介
⇒ 「のぶん」という部首がある!?その由来は知って納得・本来の名称は
⇒ 「したごころ」という部首を知ってる?知ってる漢字がいっぱいあるよ
「あくび」と同じ部首を持つ意外な漢字例
既に述べたように、「あくび」を表す漢字「欠」は、そのまま部首としても使われております。
この部首を持つ漢字には、私たちが日常的によく使うものから、ちょっと意外に感じる漢字まで、さまざまなものがあります。
次(じ)
欠を部首に持つ漢字のトップは「次(じ)」という漢字です。
これは「欠」の偏に「にすい」ではなく「二」が付いた形で、「口を大きく開けて一息ついている人」の絵から産まれたと考えられます。
本来の意は「休憩すること」なんです。
「次」が「あくび」と関係あるなんて、普段はあまり意識しませんよね。
歇(けつ)
「歇(けつ)」も「次」と同じで「いったん休む」ことを表す漢字です。
「間歇」とは「何かが起きたり休んだりを繰り返す」ことで「間歇泉」なんて言葉があります。
現在では、「間欠」と書くことも多いようです。
欧(おう)
「欧(おう)」の正式表記は「歐」。
欧州でヨーロッパのイメージが強い漢字ですが、「欧羅巴(ヨーロッパ)」から来た当て字です。
本来の意味は「大きく口を開けてモノを吐きだす」ことです。
歌(うた)
さらに、「歌(うた)」も意外な一例です。
この漢字、もともとは大きく口を開けて声を出す様子を表しています。
これも、人の動きや感情の表現に関わる漢字として、「あくび」との共通点が感じられます。
欲(よく)
また、「欲(よく)」という字も「欠」を含む漢字です。
これは「欠」に「谷(たに)」を組み合わせたもので、「何かを手に入れたいと強く思う」ことです。
人間はしばしば強い感情を表すために大きく口を開けることから来る漢字の一つです。
歓(かん)
「歓(かん)」も、強い感情を表す漢字です。
訓読みすれば「よろこぶ」で、「人々が声を上げてよろこび合う」ことを表しています。
正式には「歡」だったようです。
このように、「欠」の部首を持つ漢字は、人の欲求や行動、感情などを表すものが多いのが特徴です。
単なる部首と思いきや、その成り立ちには深い意味が隠されていることがわかります。
身近な漢字に潜む意外な共通点を探すのも、漢字を学ぶ楽しみの一つと言えるでしょう。
最後に
「あくび」を表す漢字には「欠」が使われており、この「欠」自体が部首としても使われる重要なパーツです。
漢字の構造において部首は意味や分類を示す手がかりとなり、「欠」は「あくび」「けつぶし」とも呼ばれます。
口を開けて何かを求めるような形から生まれたこの部首は、人の動作や感情、欲求などを表す漢字に多く使われています。
たとえば「次」「欲」「歌」など、意外な漢字にもこの部首が含まれており、漢字の成り立ちを知ることで日常語の奥深さや日本語の美しさを再発見できます。
■思えば、「ある言葉を漢字で書くと」の記事も増えてきました



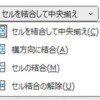





 60爺
60爺




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません