にんにくの漢字は「大蒜」!意味・由来・複数の別表記も大公開
にんにくの漢字は「大蒜(にんにく)」です。
日常ではひらがなで書かれることが多い「にんにく」ですが、漢字では「大蒜」と表記します。
この記事では、にんにくの正しい漢字表記を結論から示したうえで、意味や由来、そして、複数の漢字表記までを、できるだけ分かりやすく紹介します。
にんにくの漢字表記(正しい表記とその他の表記)
にんにくの漢字表記として、一般に正しいとされるのは「大蒜」です。
以下に紹介する表記の多くは、古い文献表記や当て字、植物名として使われてきたものです。
- 忍辱
- 蒜
- 葫
- 人肉
- 胡蒜
- 蒜肉
- 韮葱
始めに「大蒜」の由来をのべてから、他の表記の由来も並べていきます。
大蒜
にんにくの漢字表記で有名なのは、この「大蒜」ですよね。
実際、いろいろな国語辞典で「にんにく」を引いてみると、この漢字表記が現れます。
その由来なんですが、にんにくの古名は「ひる(蒜)」だったんです。
即ち、鱗茎を食用とする臭いの強い(ネギ属の)植物(にんにくもそうですし、ノビルも含みます)を指していました。
そこで、特にノビルと区別する際に、オオヒル(大蒜)と言ったんですね。
Xで「ニンニク 漢字」で検索すると、「大蒜」がたくさん出てきて、間違いなくトップでしょう!
「大蒜」は中国での表記が由来です。
「中国語翻訳⇒検索」で、「大蒜」を日本語に訳してみると「にんにく」と出ました。

ちなみに、漢方での生薬名は、同じ表記を用いますが、「たいさん」と呼ぶんですよ。勉強になりますね!
にんにくが渡来したのは、百済が日本に帰服した頃、持ち込まれたのではないかと考えられています。
ただ、その当時は、香辛料(薬草)や強壮剤として使われていたようで食品ではなかったんですよ。
忍辱
「忍辱」の本来の意味は「恥をしのぶこと」で「にんにく」は呉音読みです。
この「忍辱」の由来にはいくつかの説があるんですよ。
- 僧侶が、忍辱の修行としての荒行に耐える体力を養うために食べたこと
- 健康維持のために臭気を堪え忍んで食べた
- 強烈な臭気を隠して食べたことによる隠語
もともと、仏教世界では、精力のつく「にんにく」は、人間の心を乱し、魂を失わせるという理由で「不浄のもの」とされていました。
禅寺や律寺などの門前に建てる石碑で「不許葷酒入山門(葷酒山門に入るを許さず)」のように刻まれます。
ここにある、「葷」はニンニク・ニラ・ネギ等の臭気や辛味の強い野菜を指しています。
しかし、厳しい修行に耐えるためのスタミナ源としてこっそり食べていた僧も多かったようです。
そんなところから、「忍辱」という漢字表記は生まれたんですね。
※驚きの漢字表記はこちらにも。
蒜
蒜は、上述の「大蒜」の項で記載したように、鱗茎を食用とする臭いの強い(ネギ属の)植物の総称です。
この漢字は、音読みが「サン」で、訓読みが「ひる・ にんにく」です。
意味は、『①ひる。のびる。ユリ科の多年草。 ②にんにく(大蒜)。強い臭気がある』ですね。
この言葉も、中国の言葉が由来です。
「大蒜」の時と同様に、「中国語翻訳⇒検索」で、この漢字を日本語に訳してみると「にんにく」と出ました。
葫
漢和辞典を引いてみました。
意味は、「草の名。中国原産。根茎を食用・薬用にする。大蒜(タイサン)。にんにく。おおびる」です。
まさしく、「にんにく」を指していますね。
広辞苑でも、「にんにく」の漢字表記に、上述の「大蒜」に並んで、この表記が載っていますよ~。
ただ、この漢字を「中国語翻訳⇒検索」で、日本語に訳してみると「ひょうたん」になってしまいました!
漢和辞典には、「葫蘆(コロ)とは、ひょうたんのこと。ふくべ。」とあります。
人肉
穏やかではない漢字表記が出てきました。
確かに、人=ニン、肉=ニクですから、にんにくと読めますが、普通、この漢字表記を見たら、「ジンニク」と読んでしまいますよね。
そういう方たちの twitter を見つけました。
正しい漢字ではありませんが、「醤油を正油」って書くように、「にんにくを人肉」って書くことがあるんですねエ。
ちょっとびっくりしますが、手書きで書くときに適当な当て字を使ったと考えればいいと思います。
どちらにしろ、正式な表記ではないようですな!
胡蒜
この漢字表記の先頭にある「胡」ですが、古代中国では中央アジア(中国の北方・西方)を指す言葉だったのです。
実際、漢和辞典にも「中国の北方・西方など、外地の産物であることをあらわすことば」とあります。
「胡」については、トドの漢字表記の記事の「胡獱」にも似た文面があります。

「蒜」は既に述べたように「ひる」と読み、強いにおいがある植物を指します。
にんにくは中国原産ではなく、中国の外からシルクロードを渡ってきた植物だったことを示しているんですね。
「中国語翻訳⇒検索」で、中国語に「胡蒜」を入力して日本語に訳すと「にんにく」となりました。
これも、中国語が基になっていたことがわかります。
Xで「ニンニク 漢字」で検索したら、ただ一つだけ「胡蒜」がありました。
蒜肉
フム、この漢字はググっても、ほとんどヒットするサイトがありませんね。
出典は「ふりがな文庫」です。
今まで出版された作品から、にんにくのルビのある作品を抽出したモノですが、この表記は一般的ではないようですな。
出版された作品の一部を引用しておきます。
「そりゃ、こっちでいう事だよ。俺んところの蒜肉や大根のうまさはどうだ。君はいったい美食すぎるよ。あんなに肉ばかし食べては危険だぜ。胃癌だとか糖尿病だとか、おしまいはきまってる。」 フレップ・トリップ (新字新仮名)/北原白秋(著)
引用 ふりがな文庫
韮葱
この漢字ですが、「中国語翻訳⇒検索」で中国語に「胡蒜」を入力して日本語に訳すと「リーキ」となりました。
リーキとはなんでしょうか?調べてみると「西洋ねぎ」のことを指しているようです。
にんにくじゃないじゃん。
この記事の出典も、上記と同じ「ふりがな文庫」です。
この表記も一般的ではないようです。
韮葱の花の大きなやや毛ばだった紫の球にも細かな霧の小雨がかかっていた。フレップ・トリップ (新字新仮名)/北原白秋(著)
引用 ふりがな文庫
ニンニクの漢字表記全8種の由来を見てきました。
長くなりましたが、日常生活で覚えておくべき漢字表記は「大蒜」だけで十分です。
ニンニクの漢字の出し方
この章では、ニンニクの漢字の出し方を各機器で見ておきます。
- パソコンで「にんにく」変換で表示されるのは「忍辱、大蒜、葫」の3つでした!
- スマホで「にんにく」変換で表示されるのは「忍辱、大蒜」の2つです。
- テプラでは「にんにく」変換では、対象候補が出てきません。
スマホで、「葫」は「こ」変換で変換候補に表れます。
テプラで、「にんにく」を漢字で出すのは、「忍辱」は「忍(しのぶ)」+「辱(じょく)」で出すことができます。
また、「大蒜」は「大(だい)」+「蒜(ひる)」で出すことができました。
「葫」はSR300で未登録、SR530では登録されていたので、上級機種なら出すことができますね。
国語辞典では次の通りです。
- 広辞苑:葫、大蒜
- 三省堂国語辞典:大蒜
- 明鏡国語辞典:大蒜、蒜
これを見てわかるのは、食べ物としての「にんにく」の漢字表記として認知されているのは、「大蒜、葫」で、「忍辱」は他の意味で認識されているとの想像出来ます。
次の章では、海外では何と呼ぶのか一覧にしてみましたよ。
※身近にある漢字をテーマにしたクイズを厳選し、楽しみながら漢字への理解を深められる内容をお届けしています。
海外での表記
海外でのにんにくの表記を見てみましょう。
英語は、お馴染みのガーリックです。その他の国の表記を見てみると、(中国語を除いて)60爺には、全く馴染みのない表記が並びました。
| 言語 | スペル | 発音 |
|---|---|---|
| 英語 | garlic | ガーリック |
| ドイツ語 | Knoblauch | クロブラウク |
| オランダ語 | knoflook | プロプロク |
| フランス語 | Ail | アイ |
| イタリア語 | aglio | アーギオ |
| スペイン語 | ajo | アホ |
| ポルトガル語 | alho | アーリュ |
| スウェーデン語 | vitlök | ビープレク |
| ノルウェー語 | hvitløk | リープル |
| 中国語(繁体) | 大蒜 | ダウスェン |
| 中国語(簡体) | 大蒜 | ダウスァン |
| ロシア語 | чеснок | チェスロク |
発音に関しても、全く聞いたことのない発音のオンパレードでしたね!
わかったのは、英語のガーリックくらいです~。

どの発音を聞いても、にんにくだとは絶対分からないものばかりでした。まあ、外国語に才能のない60爺ですから、こんなものなんでしょうね。
記事を終わる前に、にんにくと同様に複数の漢字表記を持つモノに焦点を当てた記事を見てください。
よくある質問(にんにくの漢字)
Q1.にんにくは漢字で書かないと間違いですか?
A. 間違いではありません。
現代日本語では、ひらがなで「にんにく」と書くのが一般的です。
Q2.「大蒜」という漢字は日常生活で使いますか?
A. 日常会話や一般的な文章ではほとんど使われません。
辞書や専門的な文脈で使われる表記です。
Q3.にんにくには他にも漢字表記がありますか?
A. 「蒜(ひる)」は、にんにくを含む植物の総称として使われる漢字です。
複数の漢字表記を持つ動植物
にんにくは何と8種類もの漢字表記を持っていましたが、同様に複数の漢字表記を持つ動植物がありました。過去に記事にしたものを紹介します。
3種類の表記を持つ虫がいます。昔は、秋になると群れを成して飛ぶ光景が見られました。今は大分少なくなっちゃったようですねエ!
こちらは、何と6種類の漢字表記があります。夜になると出現して、害虫などを食べてくれます。そっとしておけば何もしませんので撃退などしないようにしてくださいね。
こっちは複数の表記を持つ花ですね。ジャスミンです。
最後に
にんにくの漢字表記について見てきました。
8種類の漢字があるのには驚きましたが、一般的には「大蒜」が正しいです。
にんにくは、中国から伝来したモノかと思っていましたが、実はさらに西から渡ってきたとは思いもよらなかったです。
更には、仏教徒関わりが出て来るとは驚きでした!
外国語表記についても、英語、中国語はまだしも、他の国の表記はサッパリわからんものがほとんどでした!
■思えば、「ある言葉を漢字で書くと」の記事も増えてきました

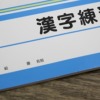







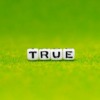




 60爺
60爺




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません