蛇(ヘビ)は何類に属するの?その理由や特徴をわかりやすくご紹介
私たちの身近な自然の中にも、ひっそりと存在感を放つ「蛇(ヘビ)」という生き物がいます。
細長い体をくねらせ、音もなく草むらを進む姿には、どこか神秘的な魅力を感じる人も多いのではないでしょうか。
一方で、突然の出会いに驚いたり、その姿に恐怖心を抱いたりすることもあります。
蛇(ヘビ)は、四肢のない身体ですばやく行動します。
そんな蛇(ヘビ)の世界をもっとよく知るためには、その分類や特徴を理解することが欠かせません。
この記事では、蛇(ヘビ)の分類に焦点を当て、それぞれの種類がどのような特徴を持ち、どのような環境で生きているのかを、わかりやすくご紹介していきます。
きっと、これまで知らなかった蛇(ヘビ)の奥深い世界が見えてくるはずです。
どうか、最後までご一緒にご覧になってください。
蛇(ヘビ)は何類なのか

始めに、蛇(ヘビ)が何類なのか見ておきましょう。
蛇(ヘビ)は、爬虫類に分類されます。
蛇(ヘビ)は爬虫類に分類される生き物です。
肺で呼吸し、冬になると活動しないなど爬虫類の特徴を持っています。
蛇(ヘビ)の生活圏は広大で、平地から4千メートルの高地までの森林・草原・耕地・湿地・荒地・砂漠の地上、樹上及び地中と、あらゆるところで生活し、一部は水中や海洋に及んでいます。
また、日本のアオダイショウのように人家周辺に棲みつく種類もいます。
大半が昼行性で日光浴による体温調節で行動し夜は巣穴に潜ります。
蛇(ヘビ)は約2千5百種が知られ、南極を除く世界の各大陸に広く分布しています。
日本には亜種を含め陸生33種、海生9種が分布しているそうです。
爬虫類は、肺で呼吸を行い、自身で体温が調整できない変温動物で、卵生(受精卵が母体内で発生し、ある程度発育してから産み出される)という特徴を持つ動物です。
体長は、ほとんどが全長1~2メートルで、最大はアミメニシキヘビの9.9メートル、最小はロイターメクラヘビなどの約10センチメートルです。
※「世界一大きい蛇」で記事を書いています。
爬虫類としての蛇(ヘビ)の特徴
蛇(ヘビ)が爬虫類であるという特徴を、呼吸・体温・産まれ方でみていきましょう。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 呼吸 | 蛇(ヘビ)は、肺で空気呼吸をします。 |
| 体温 | 蛇(ヘビ)は自分で体の熱を作り出せません。変音動物と言われる由縁です。 |
| 産まれ方 | 蛇(ヘビ)は、基本、卵生です。 |
蛇(ヘビ)は肺呼吸をしていますが、左右の肺のサイズが大きく異なっています。
左の肺は萎縮して痕跡程度になっており、その分、右肺は細長い体に収まるように長くなり、後室部分が胴の中央部まで達しているそうです。
蛇(ヘビ)の肺の役割は呼吸の他に多々あります。
- 遊泳の浮力を増す
- 胴を膨らませて威嚇する
- 強く息を吐き出してシューッという威嚇の噴気音をたてる
蛇(ヘビ)は変温動物であるため、雨で気温が低い日はヘビの体温も低いので活動もおとなしくなります。
また、天気のいい日は、体温を上げるために日当たりの良い場所に移動することもあります。
極端な暑さ寒さの環境下では休眠をします。
蛇(ヘビ)は爬虫類なので卵生だと思われるでしょうが、実は、25%に当たる種が子を産む(卵胎生)んです。
いくつかの蛇(ヘビ)が該当しますが、危険な毒蛇として有名な日本のマムシも含まれています。
卵胎生の蛇(ヘビ)が棲んでいる環境は、地中・海の中などのように苛酷な所が多いようです。
※動物の分類についてまとめた記事に、この内容を紹介しています。
※爬虫類に属する動物の記事は次の通りです。
蛇(ヘビ)の特徴
この章では、蛇(ヘビ)という爬虫類に属する生物の特化した特徴を見ていきましょう。
蛇(ヘビ)の足
蛇(ヘビ)は、全ての四肢を欠いた生物ですが、4本の手足を持つ祖先の子孫でもあります。
ただ、四肢を失う進化(退化)自体はそれほど珍しいものではない(両生類にもアイナシイモリがいる)そうです。
蛇(ヘビ)の原始的なグループ(ボア科やメクラヘビ科等)では、つめ状をした後肢の痕跡が肛板の両側に認められます。
また、生まれる前の胚の段階で、2本の脚の原基(肢芽)が確認されておるようです。
四肢がないとはいえ、蛇(ヘビ)は、その細長い身体によって、地上や樹上、水中での移動を可能にしています。
蛇(ヘビ)の食物
蛇(ヘビ)は全て肉食系です。
昆虫やミミズ等の小動物から、魚、取り、ネズミや大きな哺乳類、さらには、同じ蛇(ヘビ)を食べる蛇(ヘビ)もいます。
下顎の関節が二重になっており、大きく開くことができます。
さらに、左右の下顎の先端は伸び縮みできる靱帯で結ばれていることから、獲物に応じて別々に動かせるんだそうです。
これにより、ヤギなどの大型の動物も丸飲みが可能なんですって…・・・。
蛇(ヘビ)の鱗
蛇(ヘビ)の鱗は角質の板でできており、役割は次の3つ。
- 身体を衝撃から守る
- 乾燥を防ぐ
- 腹側の鱗は横に幅広くキャタピラーの役割をして自由に動ける
蛇(ヘビ)の持つ器官
蛇(ヘビ)の眼は、「まぶた」が固くくっついて、1枚の透明な鱗(うろこ)で覆われています。
ですから、脱皮した皮をみても、眼の位置に穴は開いていないんですよ。
眼の位置は側頭部なので、立体的な視覚は持っておらず視力は悪いんですが、至近距離で動くものはよく見えるようです。
また、鼓膜がないので聴覚は良くないのですが、地上を伝わる振動には敏感です。
鋤鼻器(じょびき)イコール「ヤコブソン器官」が発達し、嗅覚は鋭敏です。
さらに、蛇(ヘビ)特有の先が二分した舌を出し入れして、空中に漂うにおいの微粒子を運び、獲物や天敵の存在を察知します。
一部の蛇(ヘビ)の持つピット器官は、恒温動物の体温から出る赤外線を感知するモノです。
特に、マムシ類のピット器官は優れており、暗夜でも的確に獲物や天敵の位置を捉えることができます。
最後に
蛇(ヘビ)という生き物は、足もないのに自在に動いて、神秘的な魅力を感じる人もいれば、とても嫌う方もいます。
この蛇(ヘビ)の分類を見てきましたが、爬虫類であることが分かりました。
特殊な肺で呼吸し、体温を自由に扱えない蛇(ヘビ)は、日向ぼっこもするんですね。
てっきり卵生だと思っていたところ、その4分の1が胎生だったのには驚きです。
その他、蛇の持つ不思議な能力も見ていただきました。
参考
5分でわかる!セキツイ動物の分類
ヘビとは? 意味や使い方|コトバンク
卵から生まれないヘビはどれ?|WWFジャパン
Q. ヘビの仲間は何種類 – いるのですか?|徳島県立博物館
爬虫類|ウィキペディア
■追記:何類をテーマに記事をいくつか書いています





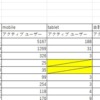





 60爺
60爺




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません